Topics
【架空電線路の強度検討の荷重を見直し】「電気設備の技術基準の解釈」が一部改正
架空電線における着雪の「定義」と「対象エリア」を改正
2024.02.22
令和5年12月26日に「電気設備の技術基準の解釈」(以下、電技解釈)が改正、同日に施行された。概要を以下にまとめる。
(1)架空電線路の強度検討の荷重に係る改正
令和4年12月に発生した北海道紋別市における鉄塔倒壊は、異常着雪に加え、鉄塔間の標高差に起因する架空電線への着雪量の差が、鉄塔両側の電線張力にアンバランスを生じさせたことが原因であった。
これを踏まえ、電力安全小委員会の審議を経て、架空電線路の強度検討の荷重に係る改正が行われた。
・着雪への対応を求める地域の条件に関する定義の改正
電線への着雪量は、降雪量に限らず、風速、風向、気温など、複数の気象条件によって影響を受けるものであるため、従来は着雪量を定量的に算定することが困難であった。このため、降雪の多い地域では着雪量が大きくなるという推定に基づき、「降雪の多い地域」で着雪への対応を求めることとしていた(電技解釈第58条第1項、第59条第5項、第93条)。
技術革新や観測データの蓄積により、地域単位で想定着雪厚さを算定することが可能となり、いわゆる「着雪マップ」が民間企業により作成、発行されるようになった。
このように、設置者が容易に着雪の多い地域を知りうるようになった状況を踏まえ、これまで「降雪の多い地域」で着雪への対応を求めることとしていたところ、改正以降は「着雪厚さの大きい地域」で着雪への対応を求めることとされた(表1~3)。
・異常着雪時想定荷重の2/3倍の荷重に耐える強度を求める対象の拡大
一定の地理的条件を満たす鉄塔には異常な着雪が生じるおそれがあるため、異常着雪時想定荷重を定義し(電技解釈第58条第1項第7号)、当該荷重に耐える強度を有するように鉄塔を施設することを求めている(電技解釈第59条第5項)。着雪による鉄塔倒壊の事例を踏まえ、対象となる地理的条件が追加された(表2)。
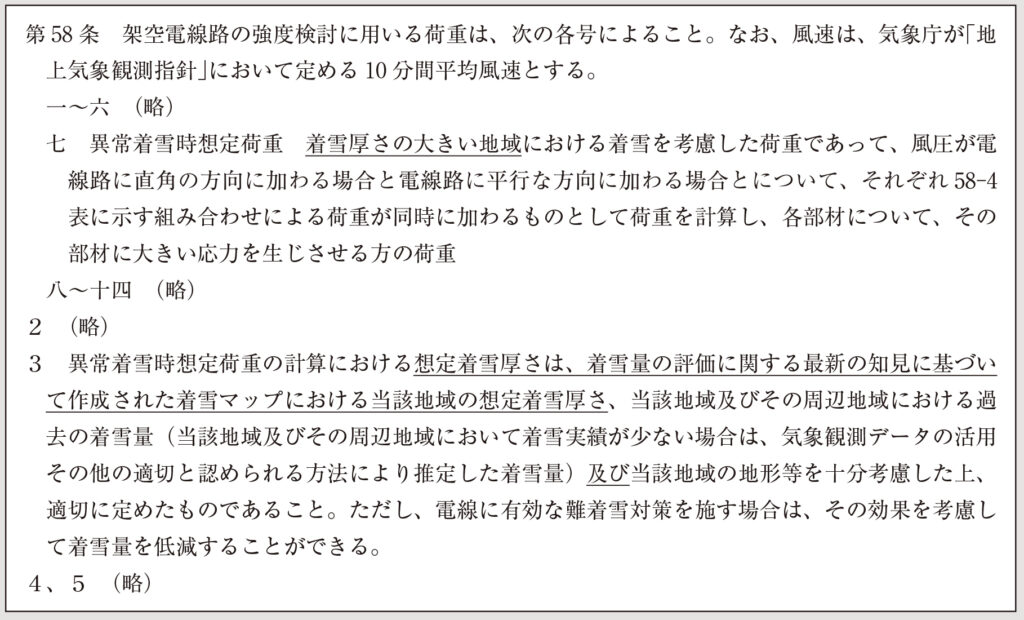
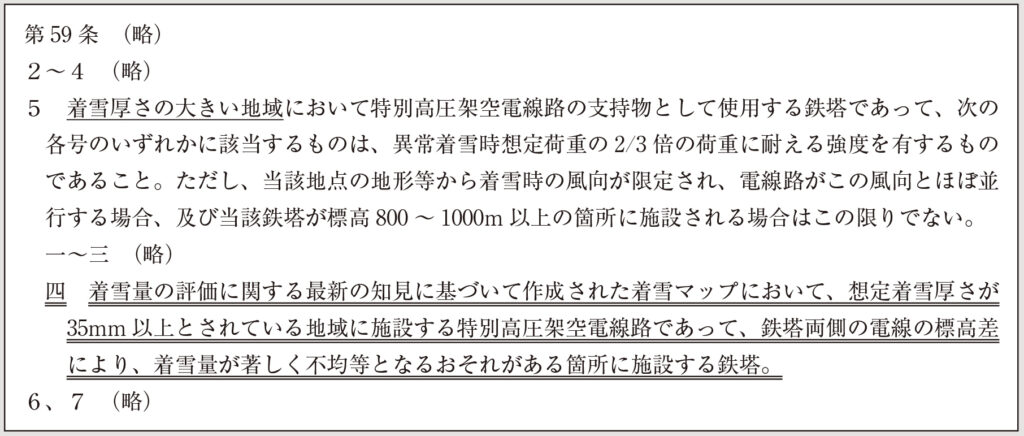
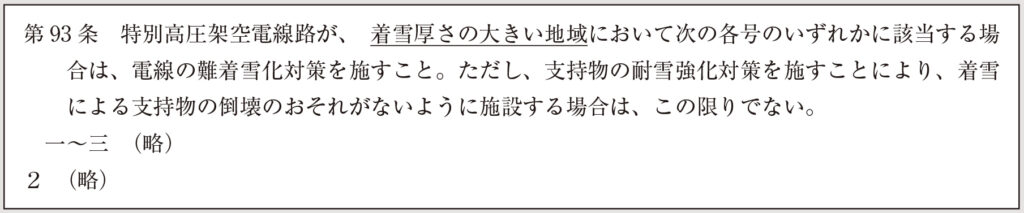
(2)電技解釈で引用しているJIS規格等の更新
JIS規格等を引用する電技解釈の条文(第46条、第56条、第57条、第129条、第130条、第175条、第197条)について、規格が最新のものに更新された。
また、廃止されている規格は代替となる民間規格、または同等の保安水準となる性能に規定された(第159条、第188条)。
なお、電技解釈に引用する規格のうち、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格については、当該委員会がホームページに掲載するリストを参照する規定とされた。
(3)最新版のIEC規格の制改定への対応
需要場所に設置される低圧の電気設備は、電技解釈第218条に規定するIEC60364シリーズの規格に基づき、施設できることとされている。
また、専門家のみが立ち入ることができる発変電所や電気室などの構内の1kV超過の電力設備は電技解釈第219条に規定するIEC61936-1に基づき、施設できることとされている。
これらのIEC規格は、随時制改定されているところ、一部を除いて電技解釈に取り入れ可能であると確認されたものについて改正された。
(文/編集部)
