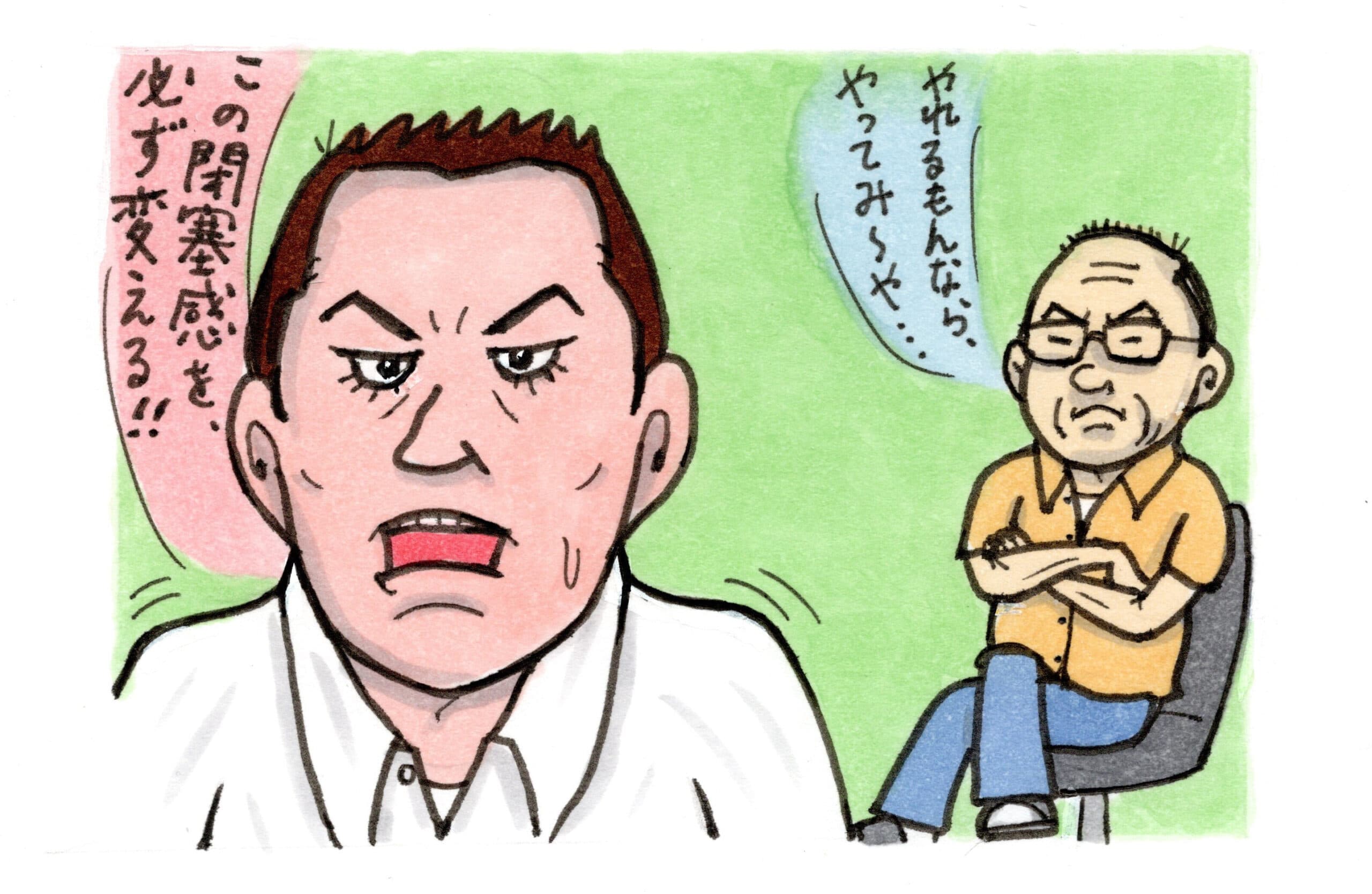Column
第1言 「鉄は熱いうちに打て」や!【電気教育、言いたい放題コラム1】
電気科教員の「はてしないグチ」
2023.07.20
第1言 「鉄は熱いうちに打て」や!
上野動物園からパンダのシャンシャンがいなくなり、一抹の寂しさを覚えている。あの愛くるしい表情や仕草に何ともいえない癒しを感じていた。
しかし、何年か前に、トレーナーがパンダをバックヤードに連れていくシーンがテレビで放送されていた。そのときのパンダは機嫌が悪いのか、発情期なのか、かなりダダをこねて、やっとの思いでバックヤードに連れていった。
もう手に負えないといったレベルだったからか、思わずトレーナーは「ありゃ、熊やぞ。あの顔にダマされたらアカン!」とこぼす始末……。大笑いしたのは言うまでもない。
さて、いきなりパンダの話で始めたが、このコラムは工業高校の電気科で教鞭を執っていた筆者が、約40年におよぶ教員生活でため込んだ「これ、どうなん?」なネタをぶちまける内容である。
で、話を本題に戻す。
工業高校電気科のカリキュラムに「電気基礎」があった(現在は電気回路)。ご存じの人も多いと思うが、内容は電気理論だ。この科目をベースに電力、機器、制御、電子回路など、幅広い分野へ発展していく。2年生、3年生の専門課程でも「なぜ、こうなるのか?」と疑問が生じるたびに電気基礎の内容を復習するので、「電気基礎が、かえって一番難しい科目だぞ!」と指導している。
それほど電気基礎は大切な科目で、「鉄は熱いうちに打て」のごとく、1年生のうちからていねいに指導するべきだと常にアピールしている。
ところが、だ。現在の工業教育の現場では「くくり募集」により、1年生は各専門学科共通履修となっている。このとき、工業教員免許を持っているということで、場合によっては機械系の教員が電気基礎を担当するという「ねじれ」が生じてしまう。専門外だから、当然、満足した教育活動になると考えにくい。
これを行政に指摘したところで「同じ工業教員の免許でしょう? 無免許運転にはならないはずです」「電気「基礎」だから、だれでもできる簡単な内容なんじゃないの?」とうっちゃられると、まさに、お手上げ状態だ。
実際、電流と磁気や静電気の教科書を物理の教員にみせると、いつも「よくこんな難しい勉強をしているなぁ〜」と言われている。
あるときなんて、書店で電験三種の理論の問題と、某国立大学二次試験の物理の問題(静電気)を比べてみると、電験三種のほうが難問で愕然とした。
「ありゃ、物理やぞ。電気基礎の科目名にダマされたらアカン!」
電気をナメたら、感電や火災などの大事故につながる。パンダのように、野生の本能で牙をむき、ツメで引き裂かれるかもしれない……。
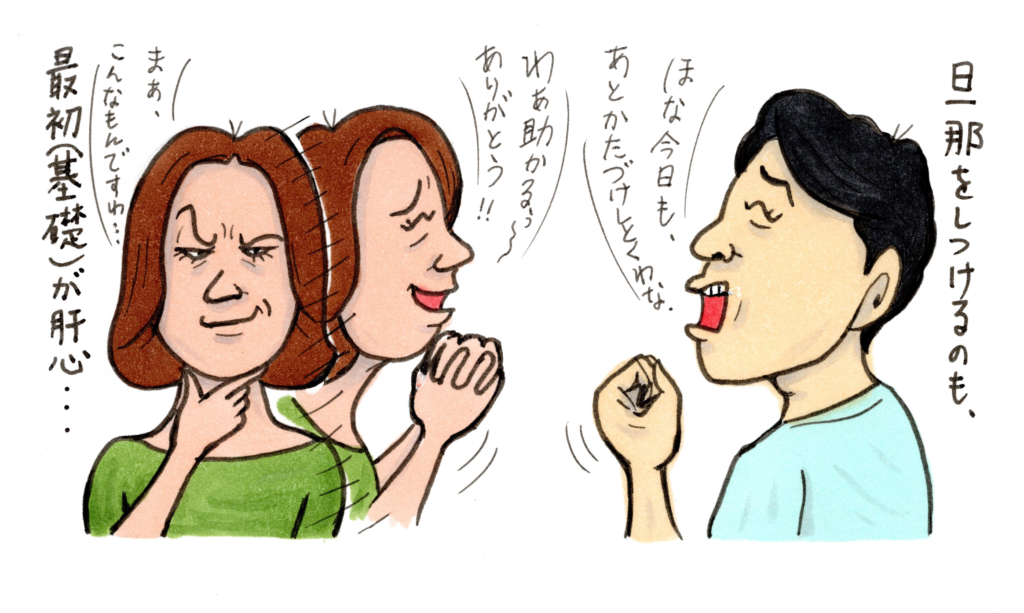
プロフィール
今出川 裕樹(いまでがわ・ひろき)
1960年生まれ。大学卒業後、電気科の教員として工業高校に勤務。時事問題をぶっこみながらポイントを説明するユニークな授業を展開。その軽妙なトークは、爆笑のうずを巻き起こしつつ、内容を理解できるということで生徒に絶大な支持を得ている。50歳を前に電験三種に合格し、現在、二種に向けて鋭意勉強中。
電気教育、言いたい放題 記事一覧
- 【第1回】「鉄は熱いうちに打て」や!
- 【第2回】「電気工事界のブラックジャック、降臨!」
- 【第3回】「破顔の秘孔をついた。オマエたちはもう、笑わずにはいられない」
- 【第4回】「電験三種認定校をレッドリストに!」
- 【第5回】「工業教育改革にドロップキック!」
- 【第6回】「三千六百五十歩のマーチ」
- 【第7回】「244/大リーグボール作戦」で工業高校改革に待った!
- 【第8回】「□いアタマを○くする」作戦で工業教育改革に喝!
- 【第9回】工業の「本質」の追求に、燃え上がれ工業教員!
- 【第10回】「答えのない答え」は、ホントにみつかるのか?
- 【第11回】「働き方」より「働きがい」の改革を!
- 【第12回】「パワハラ」「いじめ」の群雄割拠
- 【第13回】「キミの胸に書類、書類come back to you」
このシリーズ
電気教育、言いたい放題